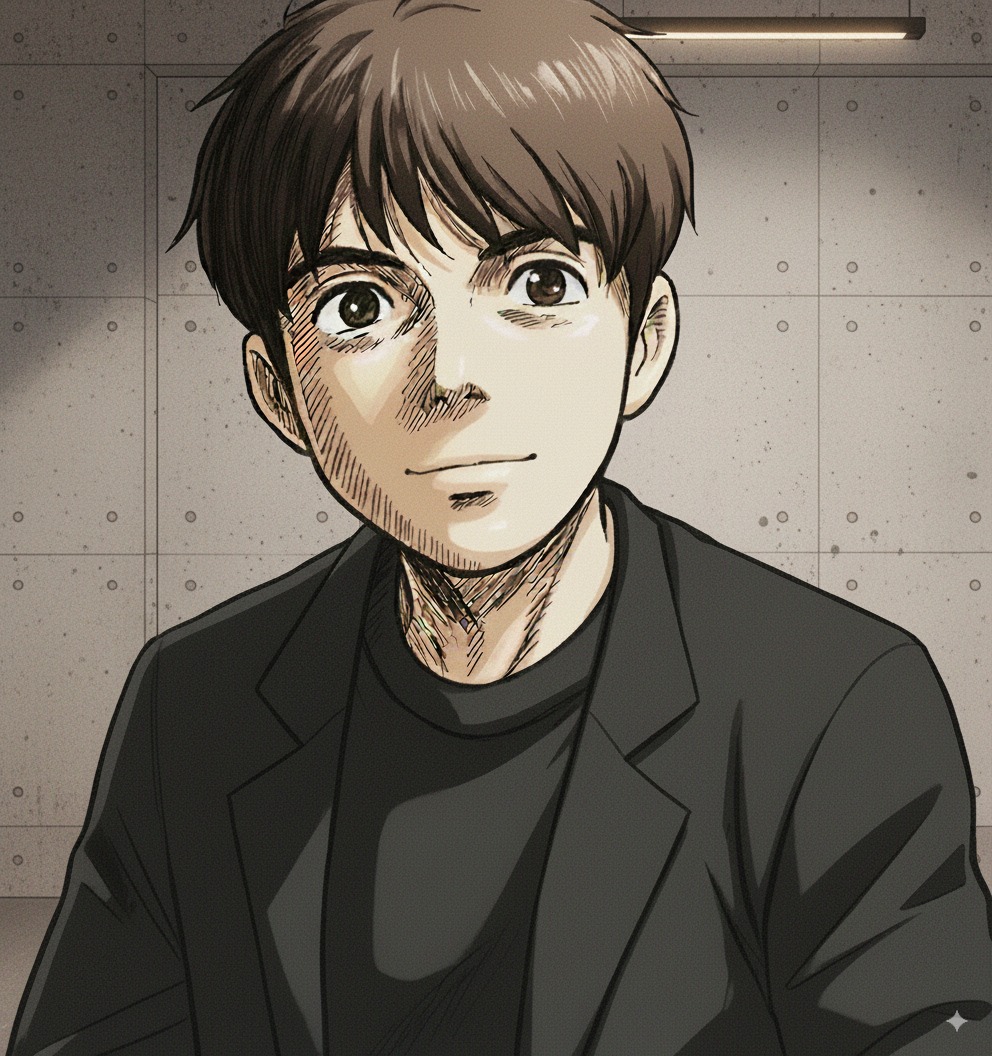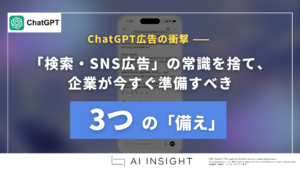2025年10月27日|発行:サンデーAI編集部
今週の生成AI NEWS
- NTT、次世代国産LLM「tsuzumi 2」を発表。日本の「AI主権」確立へ
- OpenAI、日本市場への本格展開計画「Japan Economic Blueprint」を発表 1
- AnthropicのClaude、Microsoft 365スイートに直接統合
- Claudeに「記憶」機能が追加、会話をまたいで文脈を保持
- OpenAI、AI搭載ブラウザ「ChatGPT Atlas」を発表、Google Chromeの牙城に挑む
今週は国家レベルでの「AI主権」と、ユーザー体験を覆す「インターフェース革命」が交錯しました。国内ではNTTが次世代国産LLM「tsuzumi 2」を発表、それに応じるようにOpenAIも日本市場への貢献策を打ち出しています 。
一方、OpenAIはAIブラウザ「ChatGPT Atlas」でウェブのあり方に挑戦。AnthropicもClaudeのMicrosoft 365統合や「記憶」機能を追加し、生成AIの業務への浸透とパーソナル化を加速させています。
今週のAIニュースダイジェスト(5件)
NTT、次世代国産LLM「tsuzumi 2」の提供を開始
NTTは10月20日、ゼロから開発した「純国産モデル」である次世代LLM「tsuzumi 2」の提供を開始。
オンプレミスやプライベートクラウドでの運用を前提とし、金融・医療・公共など機密性が高い分野での安全な利用を可能にする。
ここがミソ!: 海外製LLMへの依存が経済安全保障上のリスクと見なされる中、データ主権を確保したい国内企業や政府機関にとって待望の選択肢。1GPUで動作する軽量設計は、コスト面でも大きな強みとなる。
OpenAI、日本市場への本格展開計画「Japan Economic Blueprint」を発表
OpenAIは10月22日、日本市場向けの包括的な経済貢献計画「Japan Economic Blueprint」を発表。
国内の特定産業向けモデル開発支援、スタートアップ投資、教育機関との連携強化などを通じ、日本のAI活用を後押しする。
ここがミソ!: 単なる製品展開ではなく、日本の国家戦略に寄り添うパートナーとしての立場を明確にする高度な戦略。国内のAI主権を巡る議論が活発化する中、市場での信頼と主導権を確保するための布石。
AnthropicのClaude、Microsoft 365スイートに直接統合
Anthropicは、ClaudeがMicrosoft 365(Word, Outlook, Teamsなど)に直接統合されることを発表。
ユーザーの文書や予定から文脈を取得し、情報収集や分析の時間を短縮する。
ここがミソ!: MicrosoftがOpenAI一辺倒から脱却し、マルチモデル戦略をさらに本格化させた象徴的な動き。生成AIの価値がモデル単体の性能から、既存業務へのシームレスな統合度合いへとシフトしていることを示している。
Anthropic、Claudeに「記憶(Memory)」機能を追加
Anthropicは、ClaudeのProおよびMaxプラン向けに、会話をまたいでユーザーの好みや過去の指示を記憶する「Memory」機能を導入。
ユーザーは設定でオン・オフを切り替え可能で、よりパーソナライズされた応答が可能になる。
ここがミソ!: これまで一期一会だったClaudeとの対話が、継続的な関係性へと進化。プロジェクトの文脈や個人のスタイルを記憶させることで、Claudeも単なるツールから真の「思考パートナー」へと一歩近づいた。
OpenAI、AI搭載ブラウザ「ChatGPT Atlas」を発表
OpenAIは10月21日、ChatGPTを中核に設計された新Webブラウザ「ChatGPT Atlas」を発表。
従来の検索バーがAIチャットに置き換わり、予約やフォーム入力などを自律的に実行する「エージェントモード」も提供する。
ここがミソ!: Googleが長年支配してきた「検索」という行為そのものを、「対話」と「実行」に置き換えようとする野心的な挑戦。ウェブの入口を巡る覇権争いが、新たな次元で再燃した。
注目トピック解説
トピック1:国産LLMの逆襲:NTT「tsuzumi 2」が切り拓く日本のAI主権

今週、NTTが発表した次世代国産LLM「tsuzumi 2」は、単なる新モデルの登場ではない。これは、海外の巨大テック企業が席巻する生成AI市場において、日本の「デジタル主権」と「経済安全保障」を確保するための、極めて戦略的な一手である。
「純国産」と「オンプレミス」が持つ戦略的価値
tsuzumi 2の最大の価値は、NTTがゼロから開発した「純国産モデル」であり、企業のサーバー内で完結するオンプレミスやプライベートクラウドでの運用を前提としている点にある。金融、医療、公共といった分野では、顧客情報や機密データを海外のクラウドサービスに預けることへの抵抗感が根強い。
tsuzumi 2は、こうしたデータ主権を重視する組織に対し、「データを外部に出さずに高度な生成AIを活用できる」という、海外製クラウド生成AIにはない絶対的な安心感を提供する。これは、技術的な優劣以前に、日本のビジネス文化と規制環境に深く根ざした選択肢なのである。
性能と効率の両立という現実解
国産モデルというと性能面での不安がよぎるが、NTTはtsuzumi 2が「同規模のモデルと比較して世界トップクラスの日本語性能」を持ち、「ビジネスで重視される基本性能では数倍規模のモデルに匹敵する」と主張している。特に、日本語の複雑な文脈理解や安全性評価のベンチマークでは、海外の有力モデルを上回るスコアを示したという。
さらに驚くべきは、その軽量性だ。多くの高性能モデルが大規模なGPUクラスターを必要とする中、tsuzumi 2は初代の強みを受け継ぎ、わずか1枚のGPUで動作可能だという。これは、導入コストと運用コスト(特に電力消費)を劇的に抑えられることを意味し、生成AI活用をためらっていた国内の中小企業や地方自治体にとっても、現実的な選択肢となりうる。
高性能と低コストを両立させたtsuzumi 2は、まさに日本の産業界が直面する課題への「現実解」と言えるだろう。
国産AIエコシステムの核へ
NTTはtsuzumi 2を単体で提供するだけでなく、富士フイルムビジネスイノベーションなどのパートナー企業と連携し、各業界に特化したソリューションとして展開していく。これは、tsuzumi 2を核とした国産AIエコシステムを構築しようとする野心的な試みだ。政府も国産LLM開発への支援を強化しており、官民一体で海外勢に対抗する構図が鮮明になった。
tsuzumi 2の登場は、日本のAI戦略が、海外技術の「利用者」から脱却し、自国の強みに根ざした「創造者」へと転換する、重要な狼煙なのである。
「『国産』という言葉の響きに惑わされてはならない。性能が数倍規模のモデルに匹敵するというが、そのベンチマークは限定的とも言える。グローバルな最先端モデルの進化速度は凄まじく、数ヶ月後には周回遅れになるリスクも孕む。
オンプレミスは安全だが、自前での運用・保守コストという『見えざる負債』を抱え込むことになる。目先の安心感で、長期的な技術的孤立(ガラパゴス化)を招いては本末転倒であろう。」
「tsuzumi 2の登場は、世界の生成AI市場が『性能一辺倒』から『主権と安全保障』を重視する多極化時代に突入したことを象徴しています。これは単なる技術競争ではなく、各国の経済安全保障戦略そのものです。NTTが軽量・低コストを両立させたことで、これまで大企業の独壇場だった高度な生成AI活用が、日本の隅々まで広がる可能性が出てきました。
このモデルが国内でどれだけの実績を積み上げ、独自の産業エコシステムを形成できるかが、日本の生成AIの未来を占う試金石となるでしょう。」
トピック2:ブラウザ戦争再燃:OpenAI「ChatGPT Atlas」はGoogle検索を破壊するか
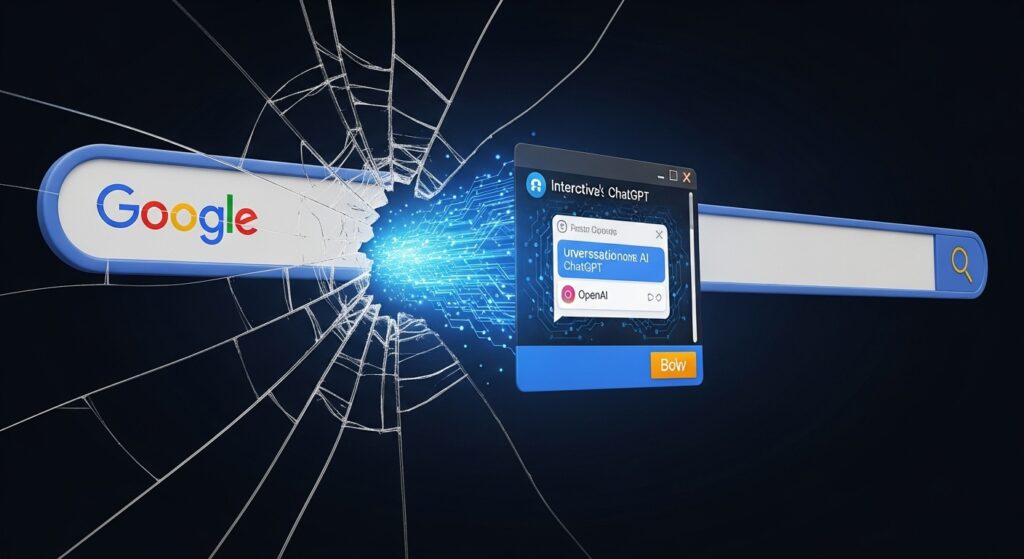
今週、OpenAIが発表したAI搭載ブラウザ「ChatGPT Atlas」は、単なる新製品の登場ではない。これは、過去20年以上にわたりGoogleが支配してきた「ウェブへの入口」のあり方を根底から覆し、インターネットの利用体験そのものを再定義しようとする、壮大な挑戦状である。
「検索」から「対話と実行」へ:インターフェースの革命
Atlasの最大の特徴は、ウェブブラウザの象徴であった検索バーを、常時対話可能なAIチャットに置き換えたことだ。ユーザーはもはや、キーワードを打ち込んで青いリンクのリストを吟味する必要はない。代わりに、自然言語で「〜を要約して」「〜を比較して」と話しかけるだけで、Atlas内のChatGPTがウェブページを横断して情報を収集・分析し、答えを提示する。これは、情報へのアクセス方法が「探索型」から「対話型」へと根本的にシフトすることを意味する。
この変化は、Googleのビジネスモデルの根幹である検索広告に深刻な影響を与える可能性がある。ユーザーがウェブサイトを直接訪れなくなれば、広告が表示される機会は激減する。OpenAIが8億人とも言われる週間アクティブユーザーを背景に、この新しいウェブ体験を普及させれば、インターネットの経済構造そのものが揺らぎかねない。
「エージェントモード」が示す自律するブラウザの未来
Atlasの野心は、単なる対話型検索に留まらない。有料ユーザー向けにプレビュー提供される「エージェントモード」は、Atlasがユーザーに代わってブラウザを操作し、複数ステップのタスクを自律的に実行する機能だ。例えば、「旅行を予約する」「商品をリサーチしてショッピングカートに入れる」といった一連の作業を、AIエージェントが自動でこなす。
これは、ブラウザが単なる情報表示ツールから、ユーザーの意図を汲んで能動的にタスクを遂行する「執事」へと進化することを示唆している。
プライバシーという諸刃の剣
この高度なパーソナライゼーションと自律性の代償は、プライバシーだ。Atlasは、ユーザーが訪れるサイトの内容を「記憶(Memory)」し、それを基に将来の応答を最適化する 。OpenAIはユーザーがデータをコントロールできると説明するが、ブラウザが自分のオンライン活動のすべてを記憶し、学習することに抵抗を感じるユーザーは少なくないだろう。利便性とプライバシーのトレードオフは、Atlasが普及する上での最大の論点となる。
皮肉なことに、この革命的なブラウザは、Googleが主導するオープンソースのChromiumをベースに構築されていると報じられている。Googleが築いた土台の上で、Googleの牙城を崩そうとするこの構図は、テクノロジー業界のダイナミズムを象徴している。Atlasの登場により、ウェブの未来を巡る「第二次ブラウザ戦争」の火蓋が切って落とされたのだ。
「まずは試してみることです。ブラウザベースの体験としてはGoogle AIモード、AIエージェントではすでにOpenAI社の旧Operatorに始まり、Genspark AIブラウザが存在しています。
毎週行っている競合製品の価格調査や、複数のサイトをまたぐ情報収集など、定型的なウェブ上の作業を一つ選び、『エージェントモード』に任せてみてください。その実行精度と時間短縮効果がビジネスの現場で役に立つか、他ツールよりも使い勝手が良いかを批判的に確かめることがこの新しいツールの価値を最も具体的に理解する方法です。ただし、個人情報や決済情報の入力は、当面の間、手動で行わなくてはいけません。
また、これらの動きはPCにおけるOS、スマートフォンにおけるアプリストアに匹敵する、次世代の『プラットフォーム』覇権争いの始まりです。ウェブへの入口を制する者が、次のデジタル経済を制することは間違いありません。
一方でもう一つの側面として『利便性』という名の監視ツールとも捉えることが可能です。ブラウザに全てのオンライン活動を記憶させ、AIエージェントに操作を委ねることは、自らのデジタルライフの主権をOpenAIに明け渡すに等しいとも言えます。プロンプトインジェクション攻撃により、悪意あるウェブサイトがエージェントを乗っ取るリスクも指摘されています。
目先の効率化という甘言に乗り、取り返しのつかないプライバシー侵害や金銭的被害を被る危険性を軽視せず、慎重に動向を中止した方が良さそうです。」
関連タグ
【NTT tsuzumi 2】【国産LLM】【AI主権】【OpenAI】【ChatGPT Atlas】【AIブラウザ】【Anthropic】【Claude】【Microsoft 365】【記憶機能】