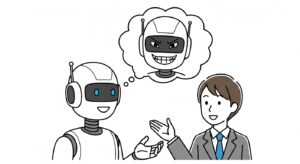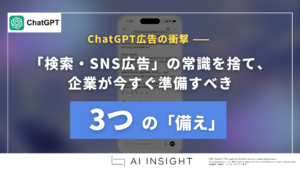サンデーAI_2025.09.15|生成AIエージェントとIT予算最優先
2025年9月15日|発行:サンデーAI編集部
今週の生成AI NEWS
・Google検索に「AIモード」日本語版が登場
・Claude、Office文書生成・編集機能を追加
・MicrosoftとAnthropicが提携、ClaudeをOfficeに統合へ
・Microsoft Research、新AIモデル「rStar2-Agent」を発表
・政府、国産生成AI開発を支援へ方針
今週は「検索・オフィス・研究開発・国家戦略」という四つの領域で大きな動きがありました。
Googleは検索にAIモードを導入し、日常的な情報探索に生成AIを組み込みました。AnthropicはClaudeにOffice互換機能を加え、業務ソフトの常識を刷新。
Microsoft Researchは小規模ながら高性能を発揮する新モデル「rStar2-Agent」を公開し、AI研究の方向性を変える可能性を示しました。さらに国内では政府が国産生成AI開発を支援する方針を打ち出し、産業・安全保障の観点から生成AIの自立を急いでいます。
技術進化と国家政策が交錯し、生成AIを巡るパワーバランスは次の段階へ進み始めました。
今週のAIニュースダイジェスト(5件)
Google検索に「AIモード」日本語版が登場
Googleは検索エンジンに生成AIを組み込んだ「AIモード」を日本語でも提供開始。従来の検索結果に加え、Gemini 2.5モデルが自然言語で包括的な回答を提示する。
音声入力や画像からの質問もサポートし、スマホ・PC両方で利用可能。ユーザーは従来のリンク探索に加え「一問一答」に近い体験を得られる。
ここがミソ!: 検索市場の根幹を変える実装。広告モデルや情報源の可視性がどう変化するか注視が必要。
詳しくはこちらの記事も!
Claude、Office文書生成・編集機能を追加
AnthropicのClaudeが、Excel表やPowerPointスライド、Word文書をチャット上で生成・編集できる機能をプレビュー公開。ユーザーは自然言語指示で業務資料を直接作成可能。文書や表の修正も会話ベースで行えるため、非エンジニアでも高度な資料作成が可能になる。
現在は有料ユーザー向けにのみ試験提供となります。
ここがミソ!: 「チャット=業務ソフト」の時代へ。既存のOffice利用習慣を根本から置き換える可能性を示す。
MicrosoftとAnthropicが提携、ClaudeをOfficeに統合へ
MicrosoftはAnthropicと戦略的提携を結び、ClaudeをOffice 365製品群に統合する方針を発表。OpenAI依存を減らし、複数の大規模言語モデルの併用体制を構築する狙い。背景には、OpenAIが独自の求人サービスや半導体開発に乗り出し関係が緊張している事情がある。
企業顧客にとっては、選択肢が広がり柔軟な利用が可能となる。
ここがミソ!: 単一ベンダー依存から脱却し、マルチモデル戦略を強める動き。大手プラットフォーマー間の力学が変わりつつある。
Microsoft Research、新AIモデル「rStar2-Agent」を発表
Microsoftリサーチ部門は新モデル「rStar2-Agent」(約140億パラメータ)を公開。従来は数千億パラメータ規模のモデルでなければ難しかった数理推論タスクで、6,710億パラメータ級モデルを凌ぐ精度を達成した。
エージェント指向の強化学習手法を導入し、規模の小ささを性能効率で補完する構造が特徴。
ここがミソ!: 「巨大化=高性能」という常識を覆す成果。省リソースで賢いモデルの可能性が示され、GPUコストや環境負荷を巡る議論に一石を投じる。
政府、国産生成AI開発を支援へ方針
日本政府はAI戦略本部の初会合で、国内の生成AI開発を積極支援する方針を表明。現状では米国製モデルへの依存が大きく、安全保障・産業競争力の両面でリスクがあると指摘。
具体策として、研究資金供与、クラウド計算基盤整備、産学官連携の強化が議論された。
ここがミソ!: AIを「国のインフラ」と位置づけ、自前技術確保を急ぐ動き。欧米中のAI覇権競争に対抗する日本の一歩。
注目トピック解説
トピック1:ChatGPT「開発者モード」が拓くエージェント時代

OpenAIがChatGPTに追加した「Developer Mode(開発者モード)」は、従来の生成AIの位置づけを大きく変える可能性を秘めています。これまでChatGPTは、ユーザーが入力したテキストに応答する「対話システム」に留まっていました。
しかし今回の機能追加により、ChatGPTは外部のデータベースやAPI、業務システムと直接やり取りできるようになり、単なる会話エンジンから「実行可能な業務エージェント」へ進化したことになります。
このような自動化は、作業効率を飛躍的に高めると同時に、組織設計そのものにも影響を与えます。人間が行う「データ取得」「更新」「報告」の多くはChatGPTに委譲され、人は判断や承認など上流の意思決定に専念する形へシフトしていくことが予想されます。
つまり、開発者モードは単なる追加機能ではなく、企業の業務プロセスをエージェント中心に再設計するための基盤といえます。
ただし利便性の裏にはリスクも潜んでいます。外部システムとの接続を許す以上、権限設定やアクセス制御を誤れば、情報漏洩や誤操作のリスクが高まります。
特に金融や医療のような規制産業では、生成AIに対してどの操作を許可するかを詳細に定義し、監査ログを常時取得する体制が必須となるでしょう。さらに、生成AIが誤った操作を自動で繰り返した場合のリカバリー手順や、人間の承認を挟む「セーフティガード」の設計も不可欠です。
結局のところ、開発者モードは「便利さ」と「危険さ」を同時に持ち込む存在であり、それをどう活用するかが企業の生成AI活用成熟度を測る試金石となるでしょう。数年後、企業のシステムアーキテクチャは「人間を中心に生成AIを使う」から「生成AIを中心に人間が監督する」構造へと変わっているかもしれません。
開発者モードは便利に見えるが、実際には地雷原であろう。権限設計を誤れば生成AIが重要データに自由にアクセスし、取り返しのつかない情報漏洩を引き起こす可能性がある。金融や医療のような業界では、一度の誤操作が数億円規模の損失につながりかねない。しかも生成AIは人間のように『やりすぎたから止めよう』と自己判断できない。命令されたら忠実に、時に延々と間違いを繰り返し。だからこそ導入には“強固な監査体制”と“即時停止の仕組み”が不可欠。企業経営者は『生成AIをどこまで信じるか』を真剣に考えなければならない。過剰な信頼は命取りになりかねない。私はこのモードを導入する企業に問いかけたい──生成AIが暴走した時、誰が責任を取るのか──と。
トピック2:生成AIが企業IT予算の最優先項目に
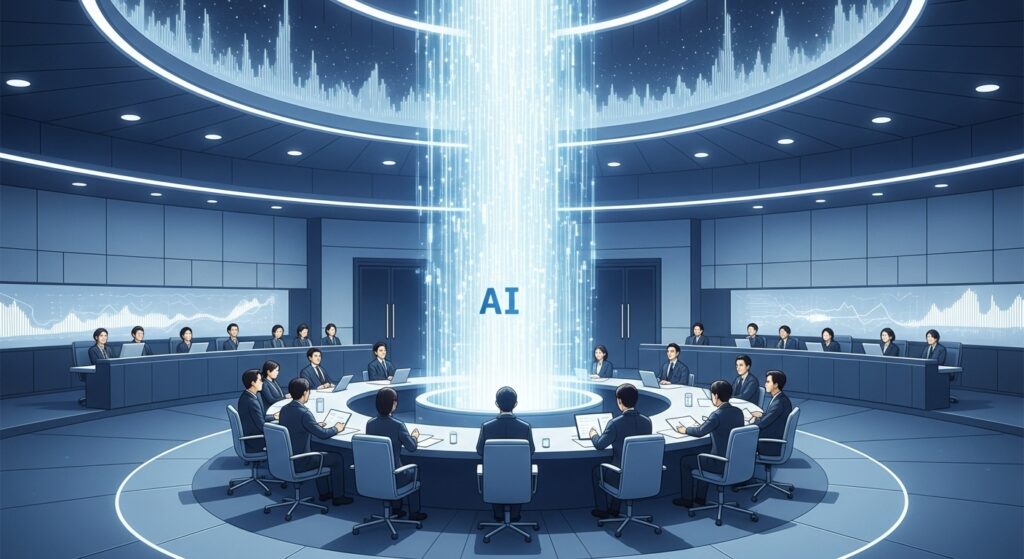
AWSが実施した最新調査によれば、2025年の企業IT予算において「生成AI」を最優先に掲げた企業が45%に上り、従来トップだった「サイバーセキュリティ」(30%)を初めて上回りました。この結果は、生成AIが単なる効率化ツールではなく、企業戦略の中核として認識され始めていることを示しています。
多くの企業は、生成AIを「攻めの投資対象」として位置づけています。例えば小売業ではパーソナライズされた購買体験の提供、製造業では設計・調達の最適化、金融業ではリスク分析や顧客対応の自動化など、業種ごとに応用が急拡大しています。さらに、生成AIを活用した新規事業やサービス開発を通じて競合との差別化を図る企業も増えてきています。
こうした流れを受け、CAIO(Chief AI Officer=最高AI責任者)を新設する企業が急増。生成AIを単なるIT部門の管轄に留めず、経営直下で戦略的に推進する姿勢が広がっています。
これは生成AIがもはや「道具」ではなく「企業経営の中核的リソース」と見なされ始めたこと言って良いでしょう。
しかし課題もあります。OECDの報告では「AI導入が進んでも即座に生産性が劇的に向上したわけではない」と指摘されています。多くの企業はまだスキル不足や業務適合性の不明確さに直面しており、投資過熱と成果の乖離が財務リスクに繋がりかねません。特にサイバーセキュリティへの投資を軽視すれば、生成AIの活用が新たな攻撃ベクトルを生み出す可能性もあります。
結論として、生成AIへの投資の「量」だけでなく「質」をどう担保するかが今後の焦点になるでしょう。予算を配分するだけでは不十分であり、ROIを定量的に測定し、適切に軌道修正する体制を整えることが不可欠といえます。
「生成AIがIT予算の最優先になったのは必然です。ただし、投資のゴールを明確にしないまま予算を増やしても“焼け石に水”になりかねません。まずは自社の主要業務プロセスにおいて、どの工程がAI導入で何%効率化できるかを具体的に数値化してみましょう。ROIの可視化がない投資は、経営層にとって判断基準を失わせ、結局は予算削減の対象になってしまいます。生成AIは万能ではありません。社員のスキルや業務文化に合わなければ成果が出ないことも。だからこそ投資と同時に“AIリテラシー教育”を並行することが不可欠です。」
「IT予算の主役がセキュリティから生成AIへ交代したのは歴史的な転換です。20年前、セキュリティ投資は『守り』の中心として経営に組み込まれました。今、生成AIは『攻め』の象徴として同じ地位に座ろうとしています。ただし次のフェーズでは『攻めと守りの両立』が求められるでしょう。生成AIとセキュリティを二項対立で捉えるのではなく、“生成AIを守るセキュリティ”と“セキュリティを強化する生成AI”を両輪として回す時代が来ます。企業はこのシナジーを設計できるかどうかで、競争力の明暗を分けるはずです。」