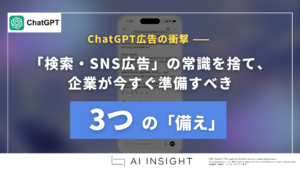サンデーAI_2025.06.30|日本の生成AI後れと逆転の処方箋
2025年6月30日|発行:AIインサイト編集部
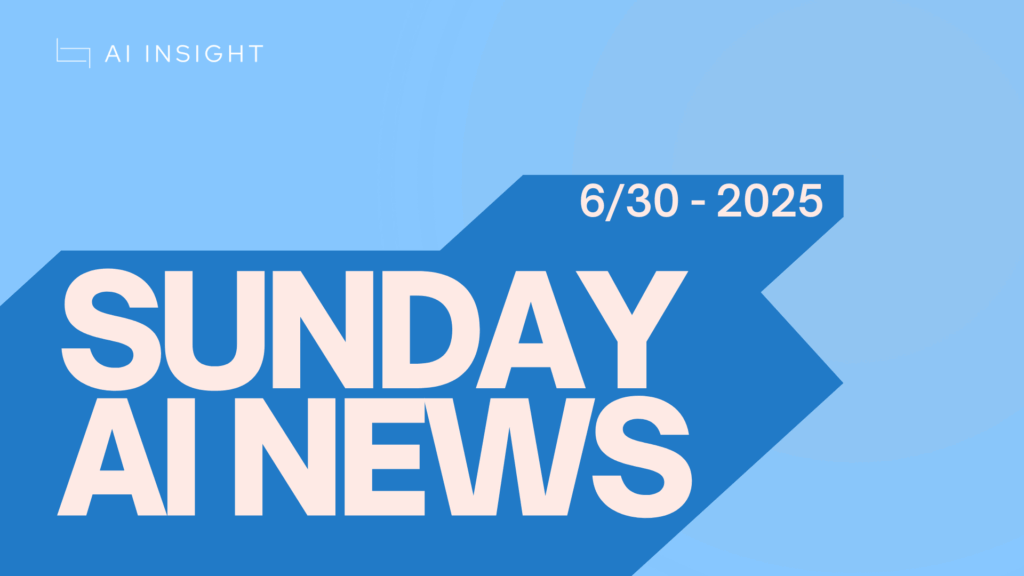
今週の生成AI NEWS
- PwCジャパン、5カ国比較の生成AI実態調査を発表
- Anthropic、東京進出へ
- 米連邦地裁、生成AIの学習巡り判断相次ぐ
- Google SheetsにAI統合、新関数「=AI」登場
- Genspark、「AIドキュメント」生成ツールをリリース
今週は、米連邦政府のフェアユースに関する判断が立て続けに判決が出たことで“AIと著作権”をめぐる動きが注目を浴びました。また、Gensparkの「AIドキュメント」やGoogleの「AI関数」など、日常のビジネス領域で生成AIがより使いやすくなった一週間でした。
今週のAIニュースダイジェスト(5件)
PwCジャパン、5カ国比較の生成AI実態調査を発表
PwC Japanグループは6月23日、「生成AIに関する実態調査2025 春 5ヵ国比較」の結果を公表しました。日本・米・英・独・中の主要企業での生成AI導入状況を比較したもので、日本企業の活用率は61%と米国の91%を大きく下回り、効果実感も「期待を大きく上回った」企業は日本9%にとどまり米国33%に遠く及ばないことが明らかになりました。
ここがミソ!: 世界に比べた日本の“生成AI後れ”がデータで裏付けられました。経営層のコミット不足やスキル人材不足といった構造的課題が浮き彫りになり、生成AI投資の目的を単なる業務効率から価値創出へとシフトしなければ、日本企業が成長機会を逃し続ける危機感を伴う内容です。
Anthropic、東京進出とClaude日本語版提供へ
生成AI「Claude」の開発企業Anthropic(アンソロピック)は6月25日、今年秋に東京にアジア太平洋地域初の拠点を開設し、日本語版Claudeを提供開始すると発表しました。
日本企業でのClaude導入が急増し、パナソニック・楽天との提携など需要拡大を受けたもので、完全ローカライズされた日本語対応AIアシスタントがスマホやPCで利用可能になります。
ここがミソ!: グローバルAI企業が日本市場に本腰を入れる象徴的な動きです。日本語版の投入で言語・文化の壁を下げ、国内企業の生成AI活用がさらに促進される可能性があります。大手プレイヤーの現地展開が進むことで、各社が競ってローカライズや現地サポートを強化し、非英語圏市場でも生成AI導入競争が本格化しそうです。
米連邦地裁、生成AIの学習巡り判断相次ぐ
米サンフランシスコの連邦地裁で、生成AIモデルの学習時における著作物利用をめぐる重要な判断が相次ぎました。6月23日、Anthropic社のAIが無断で書籍を学習データに用いた件では、「著作権で保護された書籍の無許可利用はフェアユース(公正利用)に当たる」と初めて司法が認め、AI訓練への適用可能性が示されました。
一方、6月25日にはメタ社の類似訴訟で原告の著者らの訴えが棄却。判事は「証拠不十分による却下」と断じつつ、「本判決はメタの行為が合法とのお墨付きではない」とも付言し、ケースによって判断が分かれる微妙な状況が浮き彫りとなりました。
ここがミソ!: 生成AIと著作権のルール形成に関する歴史的な一歩です。フェアユース適用が初めて具体的に示されたことで、AI開発企業にとって法的安心材料となる一方、裁判官ごとの見解の相違も表面化しました。今後は判例の積み重ねや立法によってルールが整備されるまで、不確実性を抱えつつもモデル訓練が進められることになり、各社はリスク管理と技術開発を並行して迫られるでしょう。
Google SheetsにAI統合、新関数「=AI」登場
Googleは6月25日、表計算ソフト「Googleスプレッドシート」に生成AI「Gemini」を直接組み込み、セル内からAI機能を呼び出せる新しい「AI関数(=AI)」の提供を発表しました。
ユーザーがセルにプロンプトと任意のデータ範囲を入力すると、テキスト生成・要約・分類などを自動実行でき、グラフ作成やリスト展開も含め高度な分析をセル一つで完結できるようになります。
ここがミソ!: 業務で日常的に使われるスプレッドシートに生成AIが溶け込んだ意義は大きいです。“対話型の関数”によって、複雑な関数やマクロ知識がなくても自然言語でデータ分析や資料作成が可能に。いわば**「Excel職人」がAIで誰もができる**時代への一歩であり、データ活用の民主化と生産性向上が同時に進むでしょう。また、Officeスイートへの深いAI統合はMicrosoftとの機能競争も激化させそうです。
Genspark、「AIドキュメント」生成ツールをリリース
米AIスタートアップのGensparkは、新たな文書生成支援ツール「AI Docs(AIドキュメント)」を発表しました。ユーザーが「○○の提案書を作って」などと一言指示を出すだけで、AIが関連情報のリサーチから構成作成、文章執筆、レイアウトデザインまで自動で行い、プロ品質のドキュメントを生成します。リッチテキスト(Word形式)とMarkdown双方に対応し、Genspark既存のAIスライド作成「AI Slides」や表計算「AI Sheets」と合わせ“生産性三部作”が完成した形です。
ここがミソ!: “白紙の文書作成”が過去のものになるかもしれません。専門知識がなくてもAIが下準備から仕上げまで担うことで、資料作成の所要時間を劇的に短縮できます。Gensparkは週3日勤務で済む未来「Vibe Working」を掲げており、AIによる業務自動化のビジョンを体現するサービスとなっています。もっとも、機密情報の扱いや生成内容の精度管理など課題も残っており、企業への本格浸透にはユーザー教育とガバナンス体制の整備が鍵となるでしょう。
注目トピック解説
注目トピック 1:PwC調査に見る日本の生成AI“後れ”と巻き返しの処方箋

PwC調査結果の一部。日本企業(赤色)のうち「期待を大きく上回った」と回答した割合はわずか9%(米国は33%)にとどまった。
PwC Japan発表の5ヵ国調査は、日本企業の生成AI活用が質・量ともに海外に遅れを取っている現実を突きつけました。例えば「すでに生成AIを業務で活用中」の企業は日本61%に対し米国91%、中国88%と大差があり、効果に関しても「期待以上」の企業は日本が最下位でした。
背景として、経営トップの意識差とAI人材の不足が主因と指摘されており、日本では現場任せのPoC止まりで全社展開に至らないケースが多いようです。また調査では、海外企業に多いCAIO(Chief AI Officer)設置やAIガバナンス体制が日本では遅れている点も浮き彫りになりました。要するに日本企業は「点の導入」に留まり「線での戦略」が欠如しているという構造的問題です。
では巻き返しは可能なのでしょうか?
PwCは提言として、(1)経営層の主導による全社AI戦略策定、(2)スキル人材の育成・外部招聘によるAI中核人材の確保、(3)倫理・ガバナンス重視で信頼性確保し効果最大化、の3点を挙げています。
特にCAIOの任命や社内CoE設置による統制強化は急務とされています。実際、生成AI活用で先行する米国企業では、社長直轄のAI担当役員がROI管理やリスク対応まで統括する例が増えています。日本企業も「実験段階」から脱し、トップダウンでAI活用を推進できるか否かが、この“生成AI格差”を埋める鍵を握るでしょう。
単なる効率化ツールとしてではなく、自社のビジネス変革戦略の中核にAIを位置づけられるかが問われています。
今回の調査結果は、現場で肌感覚として感じていた日本の停滞をデータで裏付けるものでした。私のクライアント企業でも、現場担当者は生成AIを使いたがっているのに経営陣がリスクを恐れて足踏みするケースが少なくありません。
まずは小さくても成功事例を社内で積み上げ、経営層の意識改革につなげることが重要です。トップダウンの号令が出れば、社内のリテラシー不足も研修や外部人材でカバーできます。幸い、日本企業は追いつく余地がまだある段階ですから、今年後半から来年前半にかけて勝負をかけてほしいですね。
国際比較でここまで差がついたのは驚きというより危機です。生成AIは各国で“ゲームチェンジャー”として位置づけられており、このままでは日本企業だけWeb3.0の波に乗り遅れるとの指摘も現実味を帯びます。ただ、幸い政府も動き始めていますし(骨太の方針への記載など)、企業サイドでも“このままではまずい”という雰囲気は高まっている。日本企業は変化が遅い反面、いったん火が付けば一斉に動く傾向もあります。
今後1~2年で経営トップのコミットが相次げば、一気にキャッチアップが進む可能性も十分あるでしょう。むしろこれからが日本の巻き返しの正念場であり、各社の本気度が試される段階だと思います。
注目トピック 2:Genspark「AIドキュメント」が拓く“お任せ資料作成”の未来
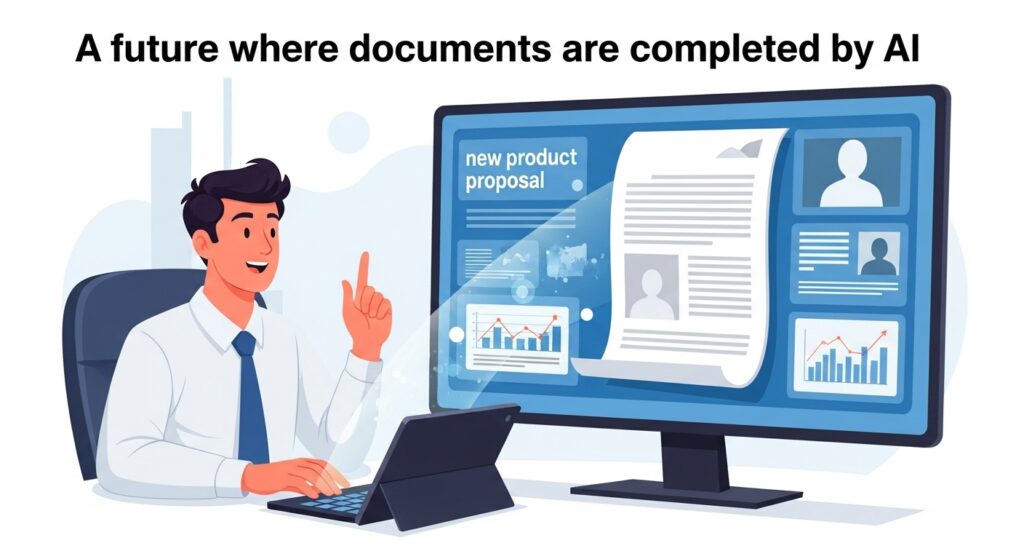
Gensparkの「AI Docs」で自動生成されたカフェメニューの例。左側にAIによるレイアウト構成案、右側に完成したメニュー表が表示されている。
Genspark社の「AI Docs」は、ユーザーが要件を一行伝えるだけでAIエージェントが文書作成を丸ごと請け負う画期的なサービスです。これまでの生成AIツールがあくまで文章作成の補助や要約にとどまっていたのに対し、AI Docsは調査・下書き・執筆・装飾まですべて自律的にこなします。
例えば「新商品の提案書を作って。市場分析とグラフも入れて」と指示すれば、関連データをネットリサーチし、適切な構成(見出しや章立て)を立案、本文を書き上げ、必要ならグラフや画像まで埋め込んだ完成度の高い提案書が生成されます。
まさに“AIに丸投げ”でプロ文書ができあがる世界が現実味を帯びてきたのです。これは資料作成に費やされていた莫大な時間(ある調査ではビジネスパーソンの60%が資料作成に時間を取られているとも)を大幅短縮しうるもので、使いこなせば8時間の作業が8分になるとも謳われています。
実際、AI DocsはWordライクなエディタとして提供され、生成後に手直しや追記も可能なため、現場の受け入れやすさにも配慮されています。さらにAI SlidesやAI Sheetsとの連携で、文章からプレゼン資料化、表データからレポート生成といったクロスアプリ展開もシームレスです。
とはいえ、“夢のような自動文書作成”には注意点もあります。
第一にアウトプットの品質管理です。AIが作る文章は一見もっともらしくても事実誤認や論理飛躍が潜む可能性があり、最終チェックの人間の目は不可欠です。また秘密情報を扱う場合のデータ取り扱いも課題です。社外非公開の情報を安易にAIに入力できないという企業も多く、AI Docsをフル活用するには社内規程の整備やオンプレミス版の要望も出てくるでしょう。
さらに、生成された文書は各社の個性やノウハウの画一化を招く懸念もあります。誰でもそれなりの提案書が作れる一方で、差別化ポイントが失われていく可能性です。
しかしGensparkは「AIで週休4日(週3日勤務)の世界」を掲げるなど大胆なビジョンを示しており、こうしたツールが働き方に与えるインパクトは計り知れません。
単なる効率化ではなく“仕事の在り方そのものを変える”ポテンシャルを持つAI Docsの登場は、各企業にAI活用の是非を突きつけることになるでしょう。
一言オーダーで勝手に提案書を作ってくれるなんて、聞こえはいいですがにわかには信じ難い部分もあります。資料作成には企業ごとのお作法や人間ならではの勘所がありますから、現場のベテランほど“AIにそんな芸当ができるのか”と懐疑的でしょう。
とはいえ、テクノロジーの進化は往々にして懐疑論を跳ね除けてきました。もし本当にAI Docsで質の高い資料が短時間で量産できるなら、使わない企業はあっという間に取り残されます。社内規定やチェック体制を整えた上で、まずは一部でも試してみる価値は大いにあるでしょう。
『ウチの提案書はAIじゃ無理』と決めつけて何もしないことこそが一番のリスクで、5年後10年後に“あの時始めておけば”と後悔する企業も出てくるはずです。夢物語かどうか、まずは使って確かめてみる姿勢が求められますね。