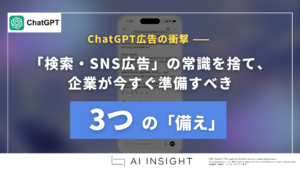サンデーAI_2025.09.01|生成AIモデル反発と画像編集革命
2025年9月1日|発行:サンデーAI編集部
今週の生成AI NEWS
・OpenAIがGPT-5を公開後、ユーザー反発を受け前世代GPT-4oの継続利用を明言
・アリババクラウドがマルチモーダル大規模モデル「Qwen-VL-Max」を発表
・ByteDanceが超長文脈対応LLM「Doubao-1.5-Pro-256k」を公開
・Microsoftが独自LLM「MAI-1」と音声モデル「MAI-Voice-1」を初披露
・Google DeepMindが画像編集特化モデル「Gemini 2.5 Flash Image(nano banana)」を発表
今週はモデル競争とユーザー体験が交錯した一週間でした。OpenAIは最新モデル公開直後にユーザーからの厳しい評価に直面し、既存モデル維持を余儀なくされました。
一方、中国勢は超長文脈やマルチモーダルで技術的優位を示し、MicrosoftはOpenAI依存を減らすべく独自モデルを打ち出しました。そしてGoogleは画像編集特化モデルでユーザー体験を刷新し、生成AI活用の裾野を広げています。
今週のAIニュースダイジェスト(5件)
OpenAI、GPT-5への反発でGPT-4oを継続利用へ
8月25日に公開されたGPT-5は「最速・最賢」を標榜したが、実際には応答の冗長化や誤答率の高さが目立ち、SNSや開発者フォーラムで「以前のGPT-4oの方が軽快で信頼できる」との声が急増。
サム・アルトマンCEOは不備を認め、GPT-4oを継続利用可能とすると発表した。OpenAIは改善プランを急ぎ打ち出し、短期的には安定化を優先する方針を示した。
ここがミソ!: 技術進化の速さとユーザー体験の差が露呈。最新モデルだから導入するのではなく、安定性や実務適合性を重視する判断が求められている。
アリババクラウド、Qwen-VL-Max発表
アリババはマルチモーダル大規模モデル「Qwen-VL-Max」を公開。テキストと画像を統合理解し、DocVQAや視覚QAベンチマークでGPT-4Vを上回る精度を記録。
国内では行政・教育分野への導入を想定し、国外クラウド市場でもプレゼンス拡大を狙う。特に大規模文書処理と画像解析の両立に強みがあり、企業が持つ複雑な文書群を効率的に可視化できる。
ここがミソ!: 中国勢がマルチモーダル分野でもトップ水準を達成。技術の国際競争が「長文理解」から「複合モード理解」へと広がっている。
ByteDance、Doubao-1.5-Pro-256k公開
ByteDanceは約2000億パラメータ規模の「Doubao-1.5-Pro-256k」を発表。混合エキスパート方式を採用し、256kトークンの超長文処理が可能。Huawei Ascend 910C上で動作し、NVIDIA依存から脱却。
さらにオープンウェイトも公開され、研究者や企業が独自ファインチューニングを実施できる。中国国内の自立戦略と国際研究コミュニティへのアピールを両立するモデルとして注目される。
ここがミソ!: 長文処理+国産インフラ+オープン公開の三拍子。中国のAI技術が閉じた市場から国際舞台へシフトしつつある。
Microsoft、独自LLM「MAI-1」と音声モデル初公開
Microsoftは自社開発のLLM「MAI-1」と音声生成モデル「MAI-Voice-1」を初披露。長年OpenAIの技術をM365 Copilotに統合してきたが、依存を減らし自前技術を組み込む戦略を鮮明にした。
両モデルはまずCopilot製品群に導入され、社内利用と外部サービス展開を両立。コスト制御や差別化を狙うだけでなく、規制リスクや競合環境に備えた自立化を進める意図が透ける。
ここがミソ!: プラットフォーマー各社は「OpenAI依存」から脱却しつつある。次は「どの領域を自社モデルで差別化するか」が競争の焦点。
Google DeepMind「Gemini banana」を正式公開
コードネームbananaで開発されていたGemini 2.5 Flash Imageを発表。最大の特徴は、人物やキャラクターの固有の外観を保ったまま服装や背景を変えるなど、一貫性を持った編集が可能になったこと。
従来課題だった「編集すると顔が崩れる」現象を大幅改善。全画像にSynthID透かしを埋め込み、ガバナンス面も強化。マーケティング、教材制作、EC商品写真の量産に実務的インパクトをもたらす。
ここがミソ!: 一貫性と信頼性の両立は画像生成AIの実用化を加速。ビジュアル制作における民主化が一歩前進した。
注目トピック解説
トピック1:OpenAI GPT-5への反発と「最新=最良」の神話の終焉
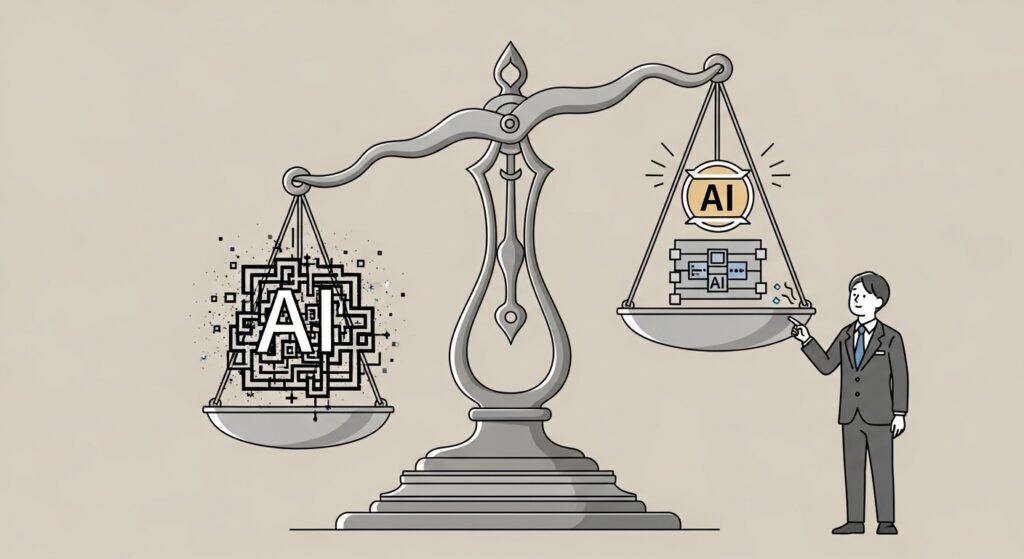
GPT-5は「最速で賢い」を売りに登場したが、現場ユーザーからは「冗長すぎる」「誤答が増えた」と不満が噴出した。結果としてOpenAIは、公開直後に前世代GPT-4oを引き続き利用可能にすると発表。これは単なる一モデルの不調ではなく、生成AIの進化とユーザー期待値のギャップが顕在化した事例だ。
実際の業務利用では「高度な推論」よりも「安定して短時間で正確な回答」が重視される。ユーザーはモデルの精度だけでなく、一貫性・速度・トーンといった総合的なUXで評価する段階に入った。最新モデルを即座に全社導入するのではなく、従来モデルとの比較検証やタスク別選択が不可欠になる。これは「1モデル支配」の時代から「複数モデル共存」の時代への移行を象徴している。
GPT-5は批判を浴びたが、企業にとっては好機です。PoC段階で4と5を並行運用し、自社の主要タスクでどちらがROIを高めるかを定量的に評価してみるのはいかがでしょうか。
しばらくは「万能モデル」は存在せず、用途別に複数モデルを組み合わせるハイブリッド利用が主流になるはずです。今回の騒動はその必然を早期に示したにすぎません。日々様々高性能モデルが登場していきますが、様子を見つつ使い慣れたツール / モデルを使用し続けるという選択肢もあるかもしれません。
トピック2:Gemini nano bananaが示す画像編集の新境地

Google DeepMindが発表したGemini 2.5 Flash Image(nano banana)は、画像生成AIにおける長年の課題である「一貫性」を突破した。
従来は背景や衣装を変えると人物の顔や体型が崩れることが多かったが、nano bananaは固有の特徴を維持したまま変更が可能。これによりEC商品写真のバリエーション生成、広告キャンペーンでのキャラクター展開、教育教材でのカスタマイズ画像作成など、即時的なビジネス価値が期待される。
さらに全生成物にSynthID透かしを埋め込み、出所追跡や不正利用対策を強化。非デザイナーでもテキスト指示だけで高度な編集ができるため、社内のマーケ担当や教育担当が即座に活用できる環境が整った。
AdobeやOpenAIの画像機能との競合において、nano bananaの強みは「速度と一貫性」。ブランド統一性が求められる実務にフィットするのは大きな差別化だ。今後は動画や3Dへの拡張も視野に、ビジュアル制作の民主化をさらに推し進めるだろう。
一貫性の進歩は評価できるが、細部の破綻は残る。実運用では人間のレビューは不可欠であり「生成AI任せ切り」は危険であろう。一方で画像生成単独の時代は終わり、テキスト・音声・動画とのマルチモーダル統合が次の本流とも言える。nano bananaはその転換点であり、動画領域への拡張が最大の焦点となるので今後のアップデートを期待したい。
関連タグ
【GPT-5反発】【ユーザー体験】【Qwen-VL-Max】【Doubao-1.5-Pro-256k】【MAI-1】【Gemini banana】